カメラの種類と構造を知る(一眼レフとファインダー)
一眼レフのファインダー
一眼レフの基本的な構造はこちら(一眼レフの基本構造)で解説していますが,一眼レフには「撮影レンズを通った光をファインダーで直接確認できる」という特徴があります.
しかし,少し厳密に言うと「ファインダーに写る像」と「実際に記録される像」では大きさが異なります.普通は実際に記録される像よりもやや周囲がカットされた範囲の像がファインダーに写ります.この比率のことを「ファインダー視野率」と言います.視野率が100%であれば,ファインダーに写る像と記録される像はまったく同じになりますが,例えば視野率が縦横90%だと,実際に記録される画面の縦横長さの90%がファインダーに写っていることになります.
視野率100%は商品撮影など厳密なフレーミングが必要な場合には必要になってきますが,通常撮影ではあまり気にする必要はありません.なぜならファインダーに写っているよりも広い範囲が実際には記録されているので,要は後でトリミングすればよいだけの話ですから・・・.ただ,「視野率100%」というのはカメラのステータスのひとつなので,あえて視野率にこだわってもよいかもしれません.
高級機種ほど視野率が高くなる傾向があり,視野率100%は限られたモデルにしか採用されていません.
※ちなみにミラーレスカメラに使われているEVFなら視野率100%は電子的に簡単に実現できます.
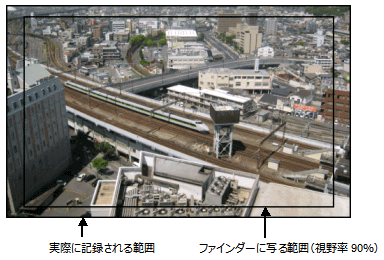
一眼レフでファインダーを覗きながらシャッターを切ると,カシャッという音と共に一瞬暗くなります.これはミラーが跳ね上がってファインダースクリーンをふさぐからです.
一眼レフの上位機種では「アイピースシャッター」を備えている機種があります.これはタイマー撮影等でファインダーから目を離してスローシャッターを切るときなどに,ファインダーからの逆入光を防ぐために使用するものです.といっても,逆入光がフィルムやイメージセンサーを感光させることはありません(撮影中はミラーが逆入光をさえぎるので).ではなんのためにアイピースシャッターを使うか?というと,正確な露出制御のためです.カメラの内部にはレンズから入ってきた光の量を測るセンサーがありますが,ファインダーからの逆入光があるとこのセンサーを狂わせてしまうのです.ファインダーに目を密着させているときには影響はありませんが,目を離すと逆入光の影響が無視できない,というわけです.露出をマニュアルで制御する場合は関係ないですが,目を離したままAEで撮影するときにはアイピースシャッターの必要性が出てきます(といっても逆入光の影響はそこまで気にする必要はないとは思いますが・・・).

以前の一眼レフの中にはファインダーごと交換できる機種(主に最高級機)もありました.例えばニコンF3などでは交換ファインダーにも多種類あり,それらを交換する楽しみもあったのですが,最近の一眼レフではファインダーが交換できる機種はほとんどなくなってしまいました.

視野率100%のデジタル一眼レフの例(35mmフルサイズ)
 Nikon D4 |
|
 Nikon D800 |
|
 Nikon D600 |
|
 Canon EOS-1D X |
|
 Canon EOS 5D Mark III |
|
視野率100%のデジタル一眼レフの例(APS-Cサイズ)
 Nikon D7100 |
|
 Canon EOS 7D |
|
 PENTAX K-5 II |
|
視野率100%の一眼レフの例(35mmフィルムカメラ)
 Nikon F6 |
|
 | カメラアーカイブス TOP |
 | 一眼レフの基本構造 |
 | 一眼レフとファインダー |
 | レンジファインダーカメラの構造 |
 | ビューカメラの構造 |
 | フィルムカメラを選ぶ(35mm判) |
 | デジタル一眼レフを選ぶ(ニコン編) |
 | デジタル一眼レフを選ぶ(キヤノン編) |
 | デジタル一眼レフを選ぶ(ソニー編) |
 | デジタル一眼レフを選ぶ(ペンタックス編) |
 | デジタル一眼レフを選ぶ(オリンパス編) |
 | デジタル一眼レフを選ぶ(シグマ編) |
 | デジタル一眼レフのスペック別総合比較 |
